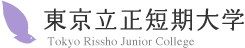ご参加いただきありがとうございます!
R-GAPは、大学での学びを先取りして様々な発見をしてもらうプログラム。
夏のオープンキャンパスで模擬授業を受講後(動画視聴を含む)、ご自宅等で課題に取り組んでいただき、お送りいただいた課題を先生が添削してお戻しするプログラムです。
課題を2科目以上提出いただいた方は、総合型選抜と学校推薦型選抜(指定校推薦)で「志望理由書」と「ワークシート」の評価を1段階アップします!
模擬授業にご参加いただき、日常生活の中にある様々な 『 ? 』 に、自然に目が向くようになりましたでしょうか?
今まで気が付かなかったことに関心を持つようになったり、もっと知りたくなったり…、そんな気持ちが芽生えていてくれたらとても嬉しいです。
ぜひ、これからも学ぶ意欲を持ち続けてくださいね。
そして、東京立正短期大学で学ぶことを楽しみにしていてください。
課題提出目標を達成されましたので、大学での学びを先取りして様々な発見をしてもらうもう一つの機会として、先生が推薦する図書をご紹介いたします。
お時間がございましたら、少しずつお手に取っていただければと思います。
きっと、これからのみなさんの学びに役に立つことでしょう。

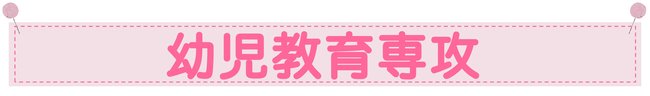

鈴木健史
-
保育の世界がまるっとわかる(笑)マンガ じんぐるじゃむっ
おおえだけいこ(小学館) -
実録 保育士でこ先生
でこぽん吾(KADOKAWA)
保育の世界を知るためには、難しい本から入るよりも、読みやすい漫画から入る方がお勧めです。
保育者も一人の人間で、試行錯誤しながら、子どもと共に成長するということや、保育という仕事のやりがいについても理解できると思います。

前嶋 元
-
ストレングス・トーク 行動の問題をもつ子どもを支え・育てる
井上祐紀(日本評論社) -
保育者だからできるソーシャルワーク
川村隆彦・倉内惠里子(中央法規) -
赤ちゃんの発達とアタッチメント
遠藤利彦(ひとなる書房)
子どもが何かができるようになると、周りの大人達は喜びます。でも、できることだけが、子どもの成長発達のために必要なことなのでしょうか。問題行動をもち、人と同じことができない子どもには良さはないのでしょうか。そうではありません。できること以外のことに実はとても大切なことが隠されています。そんな隠された秘密をこれらの図書は教えてくれます。ぜひ読んでみてください。不思議と自分自身が勇気づけられることでしょう。

中山 恵
-
どんなにきみがすきだかあててごらん
サム・マクブラットニィ(評論社) - 育ての心(
上
・
下
)
倉橋惣三(フル―ベル新書)
子どもも大人も「好き」という気持ちを表現し相手に伝えることは、容易なことではありません。ここで紹介した絵本や書籍は、私たちの気持ちを上手に汲み取ってくれているようです。小さな体で飛んだり跳ねたり「好き」を伝えようとする小さいウサギ・小さな体で保育者に興味があることを伝えようとする子どもたち。本を読んでいると、いつしか自分事になり、自分を振り返ることができる、そんな本だと思います。是非、読んでみてください。

新居直美
-
メルロ=ポンティと<子どもと絵本>の現象学-子どもたちと絵本を読むということ-
正置友子(風間書房) -
幼児期-子どもは世界をどうつかむか-
岡本夏木(岩波新書) -
あさえとちいさいいもうと
(絵本)
筒井頼子・林明子(福音館書店)
子どもの世界を哲学と絵本から…。また幼児期のなぜ?を知る書籍も読み応え十分です。
最後に、絵本から、子どもの世界をのぞいてみませんか。子どもを知るとっておきの3冊です。


有泉正二
-
弱いロボット
岡田美智男(医学書院) -
働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」
川添愛(朝日出版社) -
日常性の解剖学
G.サーサス、H.ガーフィンケル、H.サックス、E.シェグロフ(マルジュ社)
1.は、私たちの発想を転換させ、「コミュニケーション」に対する理解を深めるのにとても役立ちます。
2.は、人工知能に言語を理解させる困難を、非常に分かりやすい例えで教えてくれています。
3.は社会学の専門書で、「エスノメソドロジー」という視点から日常会話の謎の解明を試みています。

東 浩一郎
-
戦争を取材する - 子どもたちは何を体験したのか
山本美香(講談社) -
生きづらい世の中を生き抜く作法
雨宮処凛(あけび書房) -
昭和16年夏の敗戦
猪瀬直樹(中公文庫)
現実から目を背け常に楽な道に逃げようとする私にとって、本を読むということは、自分を現実社会に踏みとどまらせる手段でもあります。推薦図書 1. は、時には命に代えてでもやらねばならないことがある、ということを突き付け、 2. は自分と違う作者の視点にハッとさせられ、 3. は真実を追求することの強さと弱さに気づかされます。
いずれも説教臭い本ではなく、気軽に読めるものを選んでみました。

松本明香
-
方言萌え!?ヴァーチャル方言を読み解く
田中ゆかり(岩波ジュニア新書) -
ヴァーチャル日本語 役割語の謎 (もっと知りたい!日本語)
金水敏(岩波書店)
役割語、方言が生む役割語の機能について、わかりやすく書かれています。

横尾瑞恵
-
おどろきの心理学 -人生を成功に導く「無意識を整える」技術-
妹尾武治(光文社新書) -
こころの処方箋
河合隼雄(新潮文庫) -
何者
朝井リョウ(新潮文庫)
『おどろきの心理学』は、科学としての心理学が目に見えない「こころ」にどのようにアプローチしてきたのかが、『こころの処方箋』は、人生に役立つ「こころ」との向き合い方が分かりやすく書かれており、2冊ともそれぞれ違った観点から「こころ」を理解する奥深さを感じることができます。『何者』は、直木賞を受賞した小説ですが、社会に出る前の若者にぜひ読んでもらいたい作品です。揺らぐ自意識の中で自分らしくあろうとする現代の若者の姿がリアルに描き出されています。

福田 綾
-
観光入門 観光の仕事・学習・研究をつなぐ
青木義英・廣岡祐一・神田孝治(新曜社) -
多文化時代の観光学 フィールドワークからのアプローチ
高山陽子(ミネルヴァ書房) -
県庁 おもてなし課
有川浩(角川書店)
1. は、観光について学ぶ際の入門書として比較的読みやすいのではないかと思います。
2. は大学や短大での「観光学」という学びを少し先取りしたい場合にお勧めです。
3. は学術的な専門書ではなく小説なのですが、観光による地域活性化について現場の視点からリアルに描かれていて考えさせられることも多い一冊です。お話の展開を楽しみつつ観光というものの在り方についても考えながら読んでいただければ良いなと思います。
東京立正短期大学
Tokyo Rissho Junior College
現代コミュニケーション学科(2年制・共学)
■幼児教育専攻
■現代コミュニケーション専攻(心理・ビジネス・観光)
〒166-0013
東京都杉並区堀ノ内2-41-15
TEL 03-3313-5101 FAX 03-5377-7641